近年、日本では地震や台風などの自然災害が相次いでいます。
たとえば、能登半島地震から1年が経過し、被災地の支援や今後の備えが再度注目を集めています。
災害発生時、通常の通信インフラが停止すると安否確認や救援要請が困難になります。
そこで注目されているのが、衛星通信を用いたメッセージング技術です。
本記事では、iPhoneやAndroid端末で利用され始めた衛星経由のメッセージ機能の特徴・課題を詳しく解説し、災害時に役立つ具体的なポイントを整理します。
あなたが、もしパソコンやスマホの使い方がわからない!だれか教えて!って思っているのであれば、LINEに内容を送ってもらえれば24時間いつでもスグにその道のプロがお返事します。
今すぐ知ってる人に話を聞きたいんだけど聞けない!ってときにスパッと問題解決の回答が返ってきたらスッキリしますし、悩みから解放されて気持ちがいいですよね。
実は、今LINEでお悩みやお困りごとを無料で解決するサービスを提供しております!有料プランもありますが、無料で24時間いつでも気軽に聞けますので、ぜひあなたの悩みを解決させてください。
衛星通信メッセージングの基本!従来の通信との違い
衛星通信メッセージングは、地上の基地局を介さずに衛星に直接接続してメッセージをやり取りする仕組みです。
従来のモバイル回線がつながりにくい山岳地帯や海上、災害発生時に通信網が麻痺した状況でも、衛星さえつながればメッセージを送受信できる可能性があります。
ただし、この技術にはまだ多くの制約が存在するため、万能ではありません。
以下では、それぞれの端末別に特徴と注意点を見ていきましょう。
Appleの衛星通信メッセージング機能はiOS18以降が必須
Appleでは「iPhone 14」以降のデバイスで、iOS 18以降を搭載している場合に限り、衛星通信メッセージング機能が利用可能です。
しかし、この画期的な機能を使うにあたっては、以下のような制約がある点に注意が必要です。
1.対応範囲と互換性
現在(2025年1月時点)、米国とカナダでのみ利用できます。
受信者側もiOS 18以降を搭載したiPhoneである必要があり、日本国内やそれ以外の地域では利用できません。
2.通信事業者とSMSの制限
衛星通信をサポートしていない通信事業者の場合、サービス自体が利用できません。
また、iMessageを使えない相手に送る際はSMSを利用する必要があります。
有効なSIMカードが必要で、送信者が先にメッセージを送らないと受信できないケースもあります。
3.屋外環境と通信速度
上空と水平線がよく見える屋外でないと、衛星に接続できないことがあります。
葉が茂った場所や建物に囲まれたエリアでは、接続が不安定になります。
理想条件で約30秒、障害物がある環境では1分以上かかることもあります。
4.機能とメッセージ長の制限
グループメッセージや写真・動画の送受信は対応していません。
テキストの長さには上限があり、長文メッセージは圧縮される可能性があります。
衛星接続時はバッテリー消費が大きい点も要注意です。
Android端末での衛星通信メッセージングはGoogleの「衛星SOS」
衛星通信はiPhoneだけの機能ではありません。
Googleは「Google Pixel 9」「Google Pixel 9 Pro」「Google Pixel 9 Pro XL」「Pixel 9 Pro Fold」で、衛星メッセージング機能を提供しています。
「衛星SOS」(Satellite SOS)と呼ばれるこの機能は、主に緊急時の利用を想定したものです。
1.現状の提供範囲と利用条件
2025年1月時点で、ハワイ州とアラスカ州を除く米国限定サービスとして提供されています。
メッセージを送信できるのは911番への緊急通報のみです。
利用には「Googleのメッセージ」アプリをデフォルト設定にする必要があります。
2.衛星通信事業者「Skylo」の活用
GoogleはSkyloの衛星インフラを利用し、初期段階のサービスを展開しています。
この仕組みは、将来的な機能拡張に向けたテストも兼ねており、より広域や多機能化が期待されています。
導入前に押さえておきたい5つのチェックポイント
衛星通信メッセージングを活用するには、いくつか確認すべき事項があります。
以下の5つをしっかり把握し、自分の利用目的に合った端末やプランを選択しましょう。
- 対応エリアの確認:米国やカナダなど、現時点での利用可能地域をしっかり調べる
- 端末の対応状況:iPhone 14以降・Pixel 9シリーズなど、利用できる機種を把握する
- OSやアプリのバージョン:iOS 18以上、Googleのメッセージアプリなど必須要件を確認
- 通信事業者のサービス対応:すべてのキャリアが衛星通信をサポートしているわけではない
- 屋外環境やバッテリー管理:通信成功率と使用時間を大きく左右するため、緊急時の運用を想定する
衛星通信機能は万能ではありませんが、特定の条件下では非常に役立ちます。
上記ポイントを踏まえて、導入や利用を検討しましょう。
よくある質問:導入前の疑問を解消
Q1.日本国内での正式リリースはいつごろ?
2025年1月時点では、Apple・Googleともに米国やカナダのみでサービスを提供しています。
日本を含む他国での展開時期は公式アナウンスを待つ必要があります。
Q2.グループメッセージや画像送信はできないの?
衛星通信時は、テキストのみの送受信が主流です。
グループメッセージやマルチメディアの送受信は現状不可となっています。
Q3.屋内でも使える方法はある?
衛星との直線的な通信が前提となるため、屋内や障害物が多い場所では難しいです。
今後、基地局側のアップデートや技術進歩で改善される可能性はありますが、現時点では屋外が基本です。
まとめと次のステップ:災害時にも役立つ新たな通信手段
衛星通信メッセージングは、災害時の安否確認や救援要請など、通常のモバイル回線に頼れない場面で大きな力を発揮します。
一方で、現行のサービスは対応地域やデバイスなど、多くの制約があるため実用面に課題が残るのも事実です。
今後は技術の進化や対応エリアの拡大が見込まれ、衛星通信メッセージングの可能性はさらに広がっていくでしょう。
災害対策の一環として、「どの端末なら使えるのか」「どの地域で使えるのか」を定期的にチェックし、非常時の連絡手段の一つとして検討してみてください。
それが、能登半島地震から1年を迎えた今、改めて必要とされる防災意識の向上にもつながるはずです。
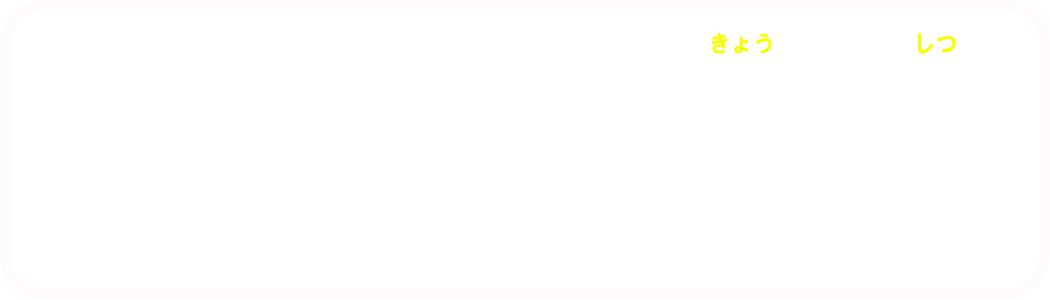

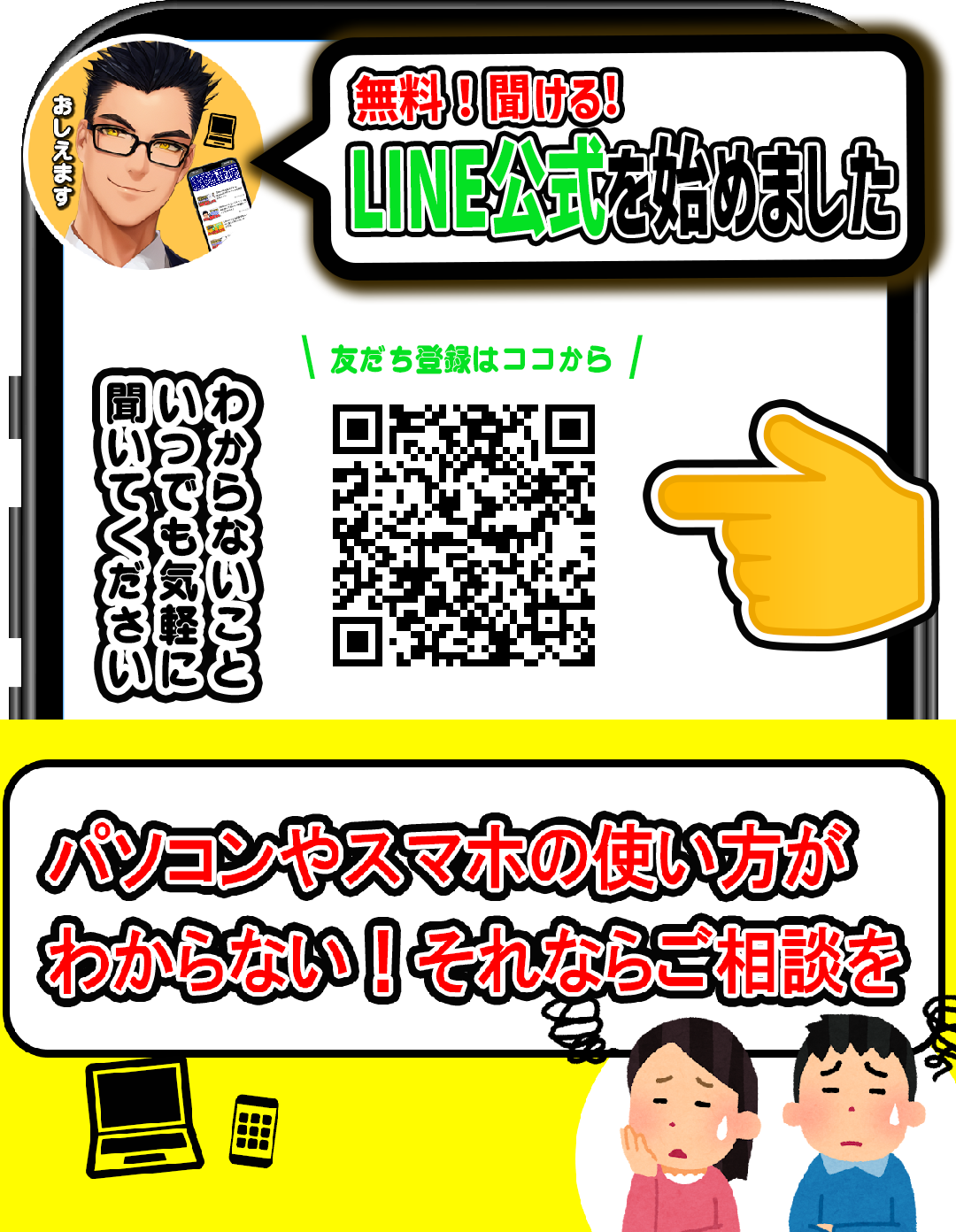


コメント